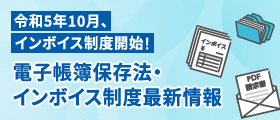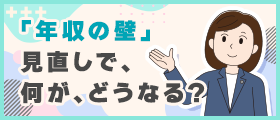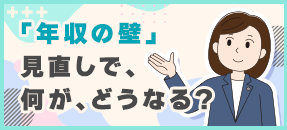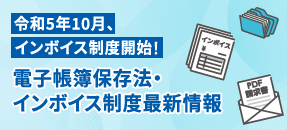令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート。

令和6年10,11月相談記録(相談8件)
●令和6年10月22日
養父が亡くなる。養父には実子が2人いる。養父の相続には関わりたくない。放棄か分割か?一切関わりたくなければ家庭裁判所へ放棄を。でなければ財産債務を受けずに分割協議書にサインを。
●令和6年11月13日
90歳の親からの贈与を考えており。その方法について暦年課税や相続時精算課税の贈与を説明。年齢から考えれば、相続時精算課税の贈与を利用して110万までの贈与が妥当。
●令和6年11月19日
推定相続人は奥さんと息子、財産2億円、相続税を考慮してどう分けたら良いかの話。小規模宅地の減額特例が賃貸に居住の息子を含めて1次、2次相続の検討か?相続時に税理士のアドバイスを受けて最終的に判断すべき。
●令和6年11月23日
遺言書作成に関して、まず、「1番目に、姪に投資信託の一部を、他は全部奥さんに。」次に「2番目に、奥さんが亡くなっていれば、姪に全部。」 と記載した方がよいと説明。様式は法務局のサンプルを参考に。
令和6年8,9月相談記録(相談9件)
●令和6年8月13日
叔父がなくなる。母や母の兄弟達が相続するが、田舎にある財産を自分の妹が継いでも良いといっている。この妹が財産を相続できるのか?でなければ取得する方法はあるか?
●令和6年8月22日
母の財産はマンションが4000万円、金融資産が2000万円程度。マンションは妹が欲しいといっている。互いに半々でいくには、妹が代償分割で1,000万円を支払うことになる?それとも共有で相続して売却か?妹は母と親しく遺言を作成する可能性が高い。
●令和6年9月6日
父が5月に亡くなる。疎遠な弟に相続を伝えるが、連絡がない。その弟がXで私を中傷している。どうすればよいか?
●令和6年9月19日
遺言の相談。ご夫婦で自宅を共有している。自宅は奥様に相続させたい。娘が2人いる。
自筆証書遺言の作成方法と法務局保管及び遺留分についての説明。
令和6年7月相談記録(相談8件)
●令和6年7月9日
母、遺言を考えているが、遺言書はどのようにしたら作成できるか?その作成の仕方のご相談。
●令和6年7月10日
父が昨年10月死亡 認知症の母に知的障害の妹、それに弟がいる。その弟が自宅を相続したいと主張している。母と妹に後見人を立てて家庭裁判所の了解をとる必要があり、弟さんの意向は困難な見込み。
●令和6年7月12日
2年前に母が死亡。 遺言書が有り、遺留分の侵害額の請求の件で姉から遺留分として約数千万円の支払いの合意書が昨年中に来ていたが、検討中で保留していた。どうすればよいか?
●令和6年7月13日
遺言書を作成して互いの財産を配偶者に与えたいが、相手がかりに先に亡くなっていたときはどうすればよいのか?との相談。

相続人でないが、全部の財産を受けることができた事例
2年前に相談に来られた方がお見えになられ、特別縁故者として妹さんと二人して全部の財産を取得できたとのご報告をいただきました。
当時のご相談は、母が亡くなった(父は既に死亡)がその母は父の後妻で、幼少の頃から一緒に暮らしていたが養子縁組をしていなかった。そのため相続人として母の財産を相続できないことがわかったのだが、財産を受け取る方法がないだろうかとの相談でした。
亡くなった父と後妻の母との間の子はおらず、後妻である母のその兄妹が相続人です。そのため相続人でない相談者が財産を受けるには、次のような方法が考えられました。
1、その兄妹が相続の放棄を行い、特別縁故者として財産を受ける方法。
2、その兄妹が相続した後、その兄妹から財産の贈与を受ける方法。
3、その兄妹が相続した後、財産を遺贈する遺言書を書いてもらい、その兄妹が亡くなってから財産を取得する方法。
4、その兄妹から家族信託を利用して財産の管理を行う方法。
以上の方法をみれば、いずれも兄妹の協力がないと進まないものです。ダイレクトに財産を受け取るのには、1の特別縁故者として財産を受ける方法がベストですが、母の全部の財産を受けることができるかは不明です。この方法は相続人がいない場合や相続人が相続を放棄した場合に家庭裁判所が財産管理清算人を置き、その財産管理清算人が財産を管理して債権債務を整理したうえで、その被相続人と生計を一にしていた者や療養看護に努めた者(特別縁故者)に財産の一部を分与するものです。
2から4の方法は、相続人が相続した後の対処法で各々それなりに手続きや期間を有するものです。
今回、不動産は換価されましたが、結果的に全部の財産を妹さんと2分の1ずつ分与されました。幼少期にお父さんが再婚し、その後妻であるお母さんと実の母のように家族として暮らしてきたことが、実の子が相続するように全部の財産を与えることに繋がったのではないかと思われます。